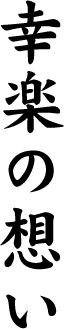
- ホーム
- 幸楽の想い
戦後の混乱期、家族の中心であり、
みんなの真ん中にいた母。
母の作る餃子が、今また家族をつなぐ。
それは創業家だけでなく、
お客さまの中にもつながっていく。
餃子のように包まれる、
家族のつながりと温もり。
80年代
人をつなげた母の餃子
中国・天津で習った餃子を母親が子どもたちのために作ったことが「幸楽」の餃子の始まり。中国からの引き揚げ寮として使われていた宇都宮・若草町の兵舎で、母・千枝は5人の子どもを育てながら、手作りの餃子を隣人にもふるまっていた。月に一度ほど催される餃子パーティーには、いつも母が中心にいた。

1960年代に母がユニオン通りの店を間借りして餃子店を開く。子どもたちも小学3・4年生になると皮を伸ばす係として活躍。やがて味が評判となり中戸祭町、若草町と店舗を移転する。現店主の康(こう)は、母の手伝いをしながら、働きづめの母が楽にならないかと餃子製造の機械化を模索していた。1972年の日中国交正常化により、中国で足止めされていた父が帰国。晴れて家族が揃う日が訪れた。

「自分たちが餃子で大きくなったように、栄養のある安心な餃子を子どもたちみんなに食べてもらいたい」そんな想いから、店を開くなら小学校の近くでと思っていた店主は、1984年に宝木町で独立。母も店を畳み、今の店を手伝うこともあった。スキーが得意だった店主は、「宇都宮みんみん」の伊藤信夫氏の主宰するスキーサークルが縁となり妻・啓子と結婚。やがて3人の息子たちが生まれる。店主の「子どもが安心して買いに来られる店」という想いが伝わるのか、近隣の子どもたちが「あともう一品のおかず」として家人に頼まれて店を訪れる姿が当たり前の光景に。

店主にとって餃子は大勢の家族と一緒にワイワイ食べた母の味。このときの思い出が、現在、子ども食堂で餃子を提供する「子どもたちに栄養満点の餃子をお腹一杯食べてほしい」という店主の想いにつながる。
2010年代
餃子で多くの人を笑顔にしたい
宇都宮の街の認知度を上げるため、市の職員が音頭を取った「宇都宮餃子」。初代会長を務めた「みんみん」の伊藤氏に請われ、全国のさまざまなイベントで餃子をアピール。最初は餃子会のメンバーが「みんみん」の餃子を焼いて試食として配布。やがては各店舗の餃子を販売するようになるが、自分たちの餃子の売り上げアップを目指したわけではなく、「餃子をお腹一杯食べて、幸せになってほしい」その一心だった。
宇都宮餃子で盛り上がることにより、結果として各店舗の売り上げが自然に上がっていった。

「多くのお客さまに食べてほしい」と思いながらも、販売数は急増。予約の分まで売れてしまい、大慌てで追加を作るなど忙しさもピークに。手作りでの対応は断念し、工場の計画を本格的に進める。店主の3人の幼い息子たちもイベントで活躍。実演販売で皮を伸ばしたり、呼び込みをしたり。それぞれが餃子のつなぐ縁を実感していた。

「幸楽」の定休日は日・月曜の連休。店主の子育て期間限定のつもりだったが、次の息子の代も子育てがはじまり、連休は継続することに。お客さまには申し訳ないと思いつつ、家族があっての幸楽の味。恐縮しつつ営業日への活力を蓄えている。

店主は理系の学部を卒業し、餃子の道に進むつもりはなかった。この道を歩むことになってから、宇都宮餃子飛躍のきっかけの「おまかせ山田商会」で餃子弁当を開発。さらに餃子を作る機械開発や工場建築で、根っからの凝り性な性格を発揮する。このこだわりが、ひと味もふた味も違うおいしい餃子づくりの源泉となっている。
〜
世代をつなぐ幸楽の餃子
「幸楽」の味は、時を経て、母の想いから、お客さまに満足してほしいという店の想いになっても変わらない。子どものときに来ていたお客さまが自分の子どもを連れて、「祖父母と来ていた」と話すお孫さんが高校生になって友人と一緒に。世代をつないでのれんをくぐる姿を、家族のように迎え入れたい、店舗スタッフ一同、そんな想いで今日も餃子を焼き続ける。

幸楽の餃子を食べに来てくれるお客さまの姿は、戦後にたくさんの家族と過ごしたにぎやかな食卓を思い起こさせる。幸楽の餃子は、今も、そしてこれからも母の味であり、温かい家族の味である。
